終わらない朝
地下鉄の車内は毎朝変わらない風景だ。私はいつものように吊り革につかまり、窓に映る自分の顔をぼんやりと見ている。蒸し暑い夏の朝、空調の風だけが心地よかった。
ふと視線を感じて隣を見ると、同じ車両に乗る若い女性がいた。彼女は薄青い表紙の本を開いている。それ自体は珍しくない。しかし、私は数日前から奇妙な違和感を覚えていた。彼女は毎朝、同じ本の同じページを読んでいるように見えるのだ。しおりの位置も指先でなぞる行も変わらない。
最初は気のせいかと思った。通勤の退屈が生んだ錯覚だろうと。しかし翌日も、その次の日も、彼女はまったく同じページを見つめている。私は半信半疑で、彼女の肩越しに覗いてみた。古びた挿絵と読めない外国語の文章――前に見たものと同じだ。
どういうことだろう。疑問が頭から離れない。彼女はなぜ毎日同じページを読み続けているのか。
ある朝、意を決して私は彼女に声をかけた。「その本、面白いんですか?」電車がトンネルに入り、灯りが揺れる。彼女はゆっくりと顔を上げ、どこか夢見心地な表情で小さく頷いた。「ええ、とても。」か細い声だった。会話はそれきり途切れ、電車は次の駅に滑り込む。彼女は本を閉じて立ち上がり、混雑に紛れて降りていった。
慌てて私も後を追った。改札を出ても、薄青い表紙が人混みの先に見える。私は必死に目で追いかけた。しかし、ビル街に出た瞬間、彼女の姿は忽然と消えていた。青い本だけが人波に揺れているような残像が、朝日の中に浮かんでは消えた。
仕事中も心ここにあらずだった。彼女は何者なのか。本当は存在しない人間ではないのか――頭に浮かんだ考えを振り払う。疲れているだけだ、そう自分に言い聞かせた。
翌朝、私は少し緊張しながら電車に乗った。いつもの座席に彼女の姿はない。胸がざわめく。昨日まであれほど確かにいたのに、幻でも見ていたのだろうか。
考え込んだまま出社し、家に帰った夜、ふと本棚を見ると、一冊の見覚えのない薄青い本が差さっていた。まさか――震える手で抜き取り、表紙を開く。見知らぬ外国語の文章とあの挿絵。間違いない、彼女が読んでいた本だ。
私は息を呑んだ。この本がなぜここに? ページをめくろうとした瞬間、自分の指先がかすんで見えた。眩暈がして本を落とす。恐る恐る手を見ると、肌が薄い膜越しに存在しているように透けている。まるで自分が現実から消えかけているようだった。
慌てて目を閉じ、深呼吸する。次に目を開けたとき、私は見知らぬ駅のホームに立っていた。朝の光の中、通勤客たちが行き交っている。手にはあの薄青い本を持っていた。混乱しながら電光掲示板を見ると、表示されている日付と時刻に覚えがない。見慣れた路線名の隣に、存在しないはずの年月日が流れている。
私は自分の頬を叩いた。夢なら覚めてくれ――そう願う。すると肩を誰かに叩かれた。振り向けば、彼女が立っていた。彼女は静かに微笑み、「次はあなたの番」と囁いた。
その瞬間、周囲の景色が滲む。はっとして目を開けると、自分のベッドの上だった。汗が額を伝っている。朝の光がカーテンの隙間から差し込んでいた。
夢…なのか? 私は荒い息を整え、辺りを確かめた。部屋の本棚に薄青い本はない。すべて夢に違いないと自分に言い聞かせる。
いつもより疲労を感じながら家を出て、駅へ向かう。電車に乗り込むと、車内にはいつもの朝が広がっていた。私は安堵し、吊り革に掴まる。額の汗を拭う。
次の駅でふと顔を上げると、少し離れた座席に彼女がいた。薄青い本を手に、静かにこちらを見ている。私は言葉を失った。夢の続きなのか、それともこれが現実なのか。彼女の唇がかすかに動いた。「おはようございます」――そう告げたように見えた。
電車は静かにトンネルへと滑り込んでいく。私の終わらない朝が、今日も始まったばかりだった。


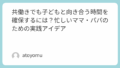
コメント