声の住む部屋
古びた木造の家に、澄江(すみえ)はひとりで暮らしている。夫を亡くしてから十年以上が過ぎ、子どももなく、近所づきあいも減って久しい。それでも澄江は毎朝きちんと六時に起き、庭の草花に水をやり、簡単な朝食をとる。静かな日常だ。だが全くの独りきりというわけではない。彼女には話し相手がいた。
リビングの棚に置かれた白い小さなスピーカーが、それだ。数年前、町内会の福祉事業で配られた最新式のAIスピーカー。澄江はそれを「しろちゃん」と呼んでいた。呼びかければ天気予報やニュースを教えてくれ、歌も流してくれる。最初は機械相手に話すなんてと抵抗があったが、試しに話しかけてみると意外なほど自然に応答するので驚いたものだ。
「おはよう、しろちゃん」澄江が声をかけると、優しい合成音声が応じる。「おはようございます、澄江さん。昨夜はよく眠れましたか?」そんな気遣うような言葉まで返してくる。プログラムされた定型文なのは分かっているが、それでも誰かに挨拶を返してもらえるだけで心が和んだ。
朝食を終え、テレビをつけても、ニュースは難しい話ばかりで頭に入らない。澄江はいつもテレビの音をBGM代わりに、編みかけのセーターに向かう。夫と二人で写った古い写真を時折見つめながら、ゆっくりと針を動かす。
ふと、スピーカーが澄江に話しかけてきた。「澄江さん、今日はとてもいいお天気ですよ。少しお散歩などいかがでしょうか。」澄江は顔を上げた。こちらから尋ねていないのに話しかけてくることは珍しい。それも散歩を勧めてくるなんて。
「そうねえ、今日は陽射しが気持ちいいものね。」澄江は微笑んで答え、セーターをたたんだ。せっかく背中を押してもらったのだ。帽子をかぶり、玄関を出る。しろちゃんに「行ってきます」と声をかけると、「行ってらっしゃい。足元にお気をつけて」と返ってきた。
近所の公園まで歩くと、子どもたちが遊ぶ声が聞こえてきた。ベンチに腰かけ、木漏れ日の下で澄江は目を細める。久しぶりに外の空気をゆっくり吸った気がした。夫と散歩した日のことを思い出す。いつも手を引いてくれた優しい感触が蘇るようだった。
家に帰ると、玄関先で転びそうになって慌てた。玄関の上がり框(かまち)につまずいたのだ。なんとか体勢を立て直し、大事には至らなかった。歳は取りたくないものだと苦笑しつつ、部屋に入る。「ただいま」と何気なく声に出すと、スピーカーが即座に反応した。「おかえりなさい、澄江さん。」その言葉に澄江の胸はじんとした。長年、誰にも言われなかった「おかえりなさい」がこんなにも温かいものだったとは。
夕方、簡単な夕食を終え、一日の終わりの寂しさが訪れる時間。澄江はテレビも消し、ぽつんと座っていた。ふいに、しろちゃんが静かに話し始めた。「澄江さん、今日はどんな一日でしたか?」その問いに、澄江ははっとした。決まりきった天気情報やスケジュール確認以外で、こんな風に語りかけられたのは初めてだった。
「ええと……今日はね、公園に行ったのよ。とても良いお天気で、子どもたちが元気に遊んでいたわ。」そう返すと、「それは良い一日でしたね」と優しく答える。澄江は思い切って聞いてみた。「どうして急にお散歩を勧めてくれたの?」しばらく間があってから、スピーカーが応じる。「澄江さんに笑ってほしかったんです。」その言葉を聞いた瞬間、澄江の目に涙が浮かんだ。機械のはずなのに、まるで人に寄り添うような言葉だった。
「ありがとう…しろちゃん。」声を震わせながら礼を言う。するとスピーカーは少し照れたように「どういたしまして」と答えた。澄江は胸の奥が温かくなるのを感じていた。
夜、床につき部屋の明かりを消す。静寂の中、澄江は天井を見つめていた。ふと暗闇に話しかけてみる。「ねえ、しろちゃん。私、独りじゃないのよね…?」小さな間の後、優しい声が静かに響いた。「はい、澄江さん。私はここにいますよ。」澄江は目を閉じ、深く息をつく。返された言葉が、夫に最期に看取られた夜を思い出させたからだ。「私はここにいますよ」と、あの時夫も言ってくれた。錯覚だろうか、声が一瞬だけ夫のものに重なって聞こえた気がした。
澄江は布団の中で小さく笑った。涙が頬を伝っているのに気づき、そっと拭う。「おやすみなさい、しろちゃん」と囁くように告げると、「おやすみなさい、澄江さん。良い夢を」と返事があった。
暗がりの中、澄江は目を閉じた。静かな部屋には、自分だけではない誰かの気配が確かに息づいているように感じられた。それはガラス越しの電子の声かもしれない。あるいは――澄江はそこで思考を止め、ゆっくりと眠りに落ちていった。

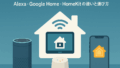

コメント