灯火の波
十数年ぶりに故郷の村に帰ってきた。盆の入りの夕暮れ、山あいの空は群青色に染まり始めている。小さな村は驚くほど静かで、虫の声だけがやけに大きく耳に響いた。
両親が相次いで亡くなってから初めて迎えるお盆だった。都会での生活に追われ、しばらく帰省していなかったが、今年はどうしても帰らねばという気持ちに駆られたのだ。駅からのバスを降り、古びた家の戸口に立つと、幼い頃の記憶が押し寄せてきた。蝉時雨、夕餉の匂い、祖母の笑顔。
荷を解き終えた頃、外がすっかり暗くなっていた。村のほうからかすかに太鼓の音が聞こえてくる。今日は「灯籠流し」の祭りの日だと思い出した。川に灯籠を流し、ご先祖や亡き人の魂を弔う古い習わし。子供のころ祖母に連れられて見に行った記憶がある。川面にゆらゆらと漂う無数の灯火の波がこの世とあの世の境に揺らめいているようで、少し怖かったのを覚えている。
私は提灯を手に、村はずれの川辺へ向かった。小道には誰の姿もなく、聞こえるのは自分の足音と虫の声だけだった。川に近づくにつれ、太鼓や笛の音色が次第に大きくなってきた。林を抜けると、開けた河原に出る。そこには人々の輪があり、浴衣を着た老若男女が集まっていた。中央では青年たちが太鼓を叩き、女性たちが笛を吹いている。私はそっと輪の後ろに加わった。
やがて祈りの声とともに、川岸に並べられた灯籠が一斉に流され始めた。橙色の光が水面に無数の揺れる帯を作り出す。灯籠の波がゆっくりと下流へ滑っていく様子に、村人たちは手を合わせて頭を垂れた。私は見よう見まねで手を合わせる。祖父母や両親の面影が脳裏に浮かび、胸が熱くなった。
その時、不意に背後から誰かに肩を叩かれた気がした。振り返ると、すぐ近くに見知らぬ老婆が立っていた。古い着物に白髪をまとめた姿は、まるで写真でしか知らない曾祖母のようにも見えた。老婆はにこりと微笑み、「よう帰ってきなすった」と穏やかな声で言った。私は言葉が出ず、ただ頭を下げた。顔を上げると、もうそこに老婆の姿はなかった。人混みの中に紛れたのか、それとも最初から幻だったのか——心臓が高鳴る。
再び川に目を向ける。灯籠の光は闇の中、遠ざかりつつあった。村人たちがゆっくりと散会し始める。私は慌てて人々の中を探した。あの老婆の姿をもう一度確認したかった。しかし浴衣姿の老女は何人かいるものの、先ほど肩に触れた気配のある人物は見当たらない。
家路につく人々に続いて私も歩き出した。祭りの後の静けさが、押し寄せる波のように辺りを包む。ふと脇の茂みから鈴の音が聞こえた気がして足を止めた。耳を澄ますと、微かに誰かの鼻歌のようなものが夜風に乗って届いてくる。懐かしい子守唄の節回しだった。祖母が私を寝かしつけるときによく歌ってくれた曲に似ている。不思議と怖さはなく、むしろ優しい気配に満ちていた。
家に戻り、仏壇に手を合わせてから床についた。まぶたを閉じると、川面に浮かぶ橙の光がまざまざと瞼に焼き付いていた。あの老婆の笑顔と声が頭から離れない。夢うつつの中で、私は祖母に手を引かれ川辺に佇んでいる自分を見た。そっと足元の水を覗き込むと、水面にいくつもの顔が揺れていた。懐かしい面影、知らない人々、そして——私自身の顔も。その全てが穏やかに微笑んでいる。
夜半に目を覚ますと、枕元にぽつりと小さな灯籠が置かれているのが目に入った。思わず身体を起こし、灯籠を手に取る。しかし触れた途端、ふっと光が消え、ただの白い和紙の箱だけが残された。胸が妙に静かだった。怖さも驚きもなく、不思議と納得している自分がいる。「おかえり」とあの老婆が言った声が、暗闇の中でまだ優しく響いている気がした。
朝になり、村の空気は嘘のようにひんやりとして澄んでいた。私は昨夜の出来事を思い返しながら家の戸締まりをする。再び都会に戻る時間だ。荷物をまとめて玄関を出ると、隣家の老婦人が庭先を掃いていた。私に気づき、「もう行かれるのかい?」と声をかけてくれた。「ええ、お世話になりました」と頭を下げる。老婦人はにっこり笑い、「また来なんせ」と柔らかい方言で言った。その言葉がなぜだか胸に沁みた。
バス停へ向かう坂道で、私は一度だけ振り返った。朝日に照らされた静かな村。誰もいない川辺に、昨夜の灯籠の残骸がいくつか引っかかっているのが見えた。川面は何事もなかったように輝いている。私は目を細め、「ただいま」と小さく呟いてから、ゆっくりと前を向いた。日常へ戻る道が、まっすぐに伸びていた。


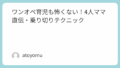
コメント